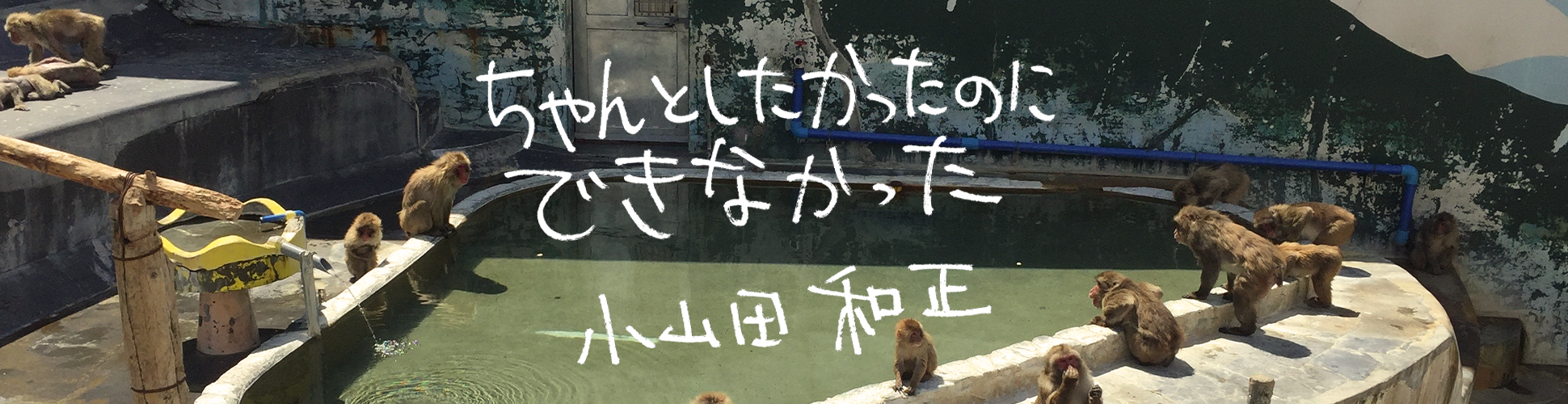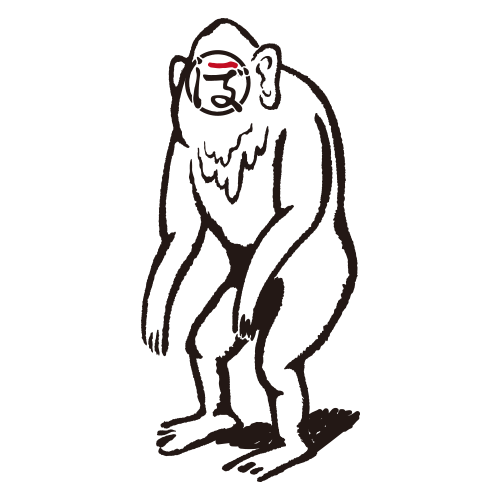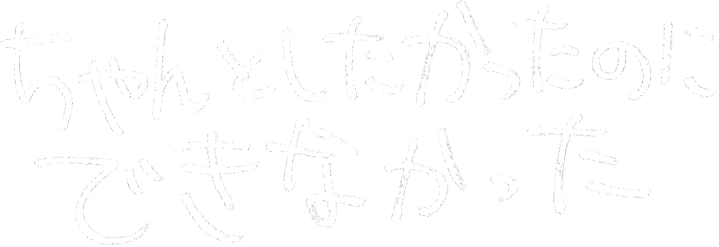 ⑥ 悲しみを暖炉で燃やす時
⑥ 悲しみを暖炉で燃やす時
HOME ‣ 連載 | ちゃんとしたかったのにできなかった ‣⑥ 悲しみを暖炉で燃やす時 (2023.1.5)

悲しみを暖炉で燃やす時
暗闇にシンシンと雪が降り続いている。朝には雪はすっかり木々も屋根もアスファルトもすっぽりと覆い、見慣れていた昨日までの景色を大きく変えてしまった。今までとは違うキリっと凍る空気は、このまま数ヶ月間、雪が積もっていくだけの時期になったことを知らせてくれる。
もう春まで僕たちはこの世界の住人になる。自然界に「白」という色は存在しないと考える時、「白」を使わずにこの景色はどんな言葉で表現できるだろう。すっぽりと光に包まれた世界、か。
彩色の世界が、無彩色に変わるこの時期、僕は「襟裳岬」の歌詞の冒頭を思い浮かべて口ずさんだりする。
北の街ではもう
悲しみを暖炉で
燃やしはじめてるらしい
(歌:森進一・作詞:岡本おさみ・作曲:吉田拓郎・1974年)
雪解けがはじまる春彼岸の頃から、今まで9ヶ月間、今年もいろいろあった。辛いことも、悔しいことも、悲しいこともたくさんあったけど、北の街では、それを暖炉で燃やす季節がはじまっている。
窓の外を見ると、僕たちが歩いていた世界に、シンシンと雪が降り続いている。積もる雪は、僕たちの悲しみの輪郭をも曖昧にして、やがて、すっぽりと光に包まれた世界に変わる。何もかも夢だったのかも。この時、この豊かさ。
北国の寒く厳しい冬は、もしかしたら、それはそれで僕たちにとって大切な「くぐる時」なのかもしれないな、と思えるようになったのは、やっと最近のことだ。
胃に穴が開く
雪は雪だ。それ以上でも以下でもないわけだけど、たとえば、ウインタースポーツという視点に立つと、雪は大いに歓迎されるものだし、寒ければ寒いほど楽しい。犬も喜んで跳ね回る。しかし、生活という視点に立つ時、それはひたすら冷たく、辛く、厳しい。朝は少し早く起きて雪かきから始まる。車もノロノロ走るので、いつもの倍の時間を要することを予定して早めに家を出る。前を走る車のテールライトが見えないくらいの猛吹雪の中をビクビクしながら運転する。帰宅すると、また車庫の前には朝と変わらず雪が積もっている。あぁ。明朝、少しでも楽ができるようにとまた雪かきをする。極寒の闇の中。
青森に帰ってきてからすぐの、ある年の冬、僕は体調の悪い日が延々と続いていた。お腹のあたりが痛い感じがして、食欲もなく、たまに酸っぱいものが込み上げてきて、ずっと気持ち悪かった。あまり長く続くので病院に行くと、胃潰瘍と診断された。「なんか強いストレスですかねぇ。思い当たることあります?」とお医者さんに尋ねられたが、何も思い当たらなかった。その後、たまたま会った友人にそのことを話すと、すぐに答えが返ってきた。「雪だよ、雪。今年の大雪じゃ誰だってストレスを抱える。俺もなったことがあるけど、自然と戦おうと思ったら、そりゃ、胃に穴も開くよ。勝てるわけない。」
僕は、僕を過大評価している。少しの謙遜を抱きながらも、何もかもをコントロールできるかも?と、どこか奥底で信じている。そして、どうしようもないもの、意のままにならないものに必死で抗う。勝てるわけがない。胃に穴が開く。
そういう姿勢とか、態度のはなし。
理由のわからないことで
悩んでいるうち
老いぼれてしまうから
(歌:森進一・作詞:岡本おさみ・作曲:吉田拓郎・1974年)
待つ。待ち続ける。
今年の冬はまだ始まったばかりで、雪の多さがどのくらいになるのか分からないけど、去年の冬は異常な雪の多さだった。毎日、仕事の合間、朝昼晩と片付けても、片付けても、片付けても降り続き、雪を寄せる場所もなくなった。全く温度が上がらないので、雪は少しも解けることなく高く積み上がり、巨大な山になって建物を覆った。もうどうしようもなかった。なんとかその時、その時をやり過ごしながら、いつやってくるか分からない春を、ただ待つしかなかった。
その頃に、ある仏教雑誌から短い文章を依頼された。この文章が、僕の今も続く「待つとはどういうことなのか?」への興味、それを深く考え始めるきっかけとなった。
今年は例年にない大雪で長く厳しい冬でした。
それでも、ちゃんと春はやってきて、
ちゃんと日差しは暖かくなり、
雪解けの地から、
いのちが一斉に涌き出るように芽吹きはじめます。僕たちはずっと待ち続けています。
待つことは、どうしてこんなに長く厳しいのでしょう。
きっと、僕たちにはどうにもならないことがある、
それを明らかにされ続けられるからなのかもしれません。春、夏、秋がすぎ、また冬はやってきます。
どうしようもなさを諦(つまび)らかにしながら、
それでもなお、と待ち続ける姿勢、
祈りの連続を「南無」というのでしょう。(「わげんせ(Vol.21)」青森県 日蓮宗 法永寺住職 小山田和正)
きっといつかはやってくるであろう春(未来)へ期待を寄せては、どうしようもない現実(現在)に引き戻される。その前で、自らの小ささや弱さを中途半端に受け入れながらも、抵抗を試みる。ちょうどコロナ禍における「待つ」も含めて、僕自身の中に揺らぎを感じなら、この文章を書いていた。
「待つ」ってどういうことなんだろう。今も考えを巡らせる。
津軽懇氣刺し
「待つ」ことに興味が湧いてきて以降、「待つ」についての考えを誰かに伝えてみたりもしたし、何かヒントになるかも?という本にもずいぶん触れてきた。その流れの中で、鷲田清一さんの『「待つ」ということ』をご紹介頂いた。
著者は、本書の初っ端、1章「焦れ」に、「待つことの放棄が〈待つ〉の最後のかたちである」と記し、さらに、この事態が「本書の最後まで引きずることになるであろう」と念を押している。その言葉の通り、本書を通して、さまざまな視点から〈待つ〉を論じながらも、「待つことの放棄が〈待つ〉の最後のかたちである」ことに何度も近づこうとする。
〈待つ〉は偶然を当てにすることではない。何かが訪れるのをただ受け身で待つということでもない。予感とか予兆をたよりに、何かを先に取りにゆくというのではさらさらない。ただし、そこには偶然に期待するものはある。あるからこそ、なんの予兆も予感もないところで、それでもみずからを開いたままにしておこうとするのだ。その意味で、〈待つ〉は、いまここでの解決を断念したひとに残された乏しい行為であるが、そこにこの世への信頼の最後のひとかけらがなければ、きっと、待つことすらできない。いや、待つなかでひとは、おそらくはそれよりさらに追いつめられた場所に立つことになるだろう。何も希望しないことがひととしての最後の希望となる、そういう地点まで。だから、何も希望しないという最後のこの希望がなければ待つことはあたわぬ、とこそ言うべきだろう。わたしたちがおそらくは本書の最後まで引きずることになるであろう事態、つまり、待つことの放棄が〈待つ〉の最後のかたちであるというのは、たぶんそういうことである。(鷲田清一著『「待つ」ということ』)
著者が、「待つことの放棄が〈待つ〉の最後のかたちである」に近づこうと論じる中で、僕が一番興味を持ったのは、本書13章「希い」に記される「〈時〉の喪失のなかでこそ、何を待つでもない〈待つ〉がなりたつ」という箇所だった。さらに、「〈時〉の喪失とは、〈時〉の超越ではない。そんな立派なことではなくて、うねりも厚みも強弱もない、機械のような時間のうちにじぶんを無理やり封じ込めるということである。」と続く。
「〜を待つ」という精神の様態が〈時〉の流れのなかで現在からその外へと超え出るなかでなりたつとすれば、何かを待つのではない〈待つ〉は、(現在の外ではなく)およそ〈時〉というものの外でなされるしかない。いまだ存在しないものへの希望や祈りを、あるいはもはや存在しないものへの歯ぎしりするような悔いや安らかな思い出を不可能にするような、それこそ〈時〉の喪失のなかでこそ、何を待つでもない〈待つ〉がなりたつと、先に書いたのもそのような意味においてである。ここで〈時〉の喪失とは、〈時〉の超越ではない。そんな立派なことではなくて、うねりも厚みも強弱もない、機械のような時間のうちにじぶんを無理やり封じ込めるということである。(鷲田清一著『「待つ」ということ』)
この「機械のような時間のうちにみずからを封じ込めるいとなみ」で、僕がすぐに思いついたのは、刺し子、かごあみ、青森だと、津軽塗り、裂織、こぎん刺しなどになるだろうか、そういういわゆる北国の冬の手仕事的な何かだった。古来、雪国の人たちは辛く厳しい冬の間、「何を待つでもない〈待つ〉」を続けるために、自然に、或いは知恵によって「機械のような時間のうちにみずからを封じ込めるいとなみ」を続けてきたのかもしれない。そう思うと、僕の「待つってどういうことなんだろう?」という問いの応えは、なんだ、僕の足元にありそうだという気持ちになったし、既に僕も連綿と続く「何を待つでもない〈待つ〉」時間の中に身を置いていたのだという感覚も湧いてきて、なんだか心強く思えてきた。
ではでは、既にその時間の中に居る僕も、僕なりの方法で、「何を待つでもない〈待つ〉」ために、「機械のような時間のうちにみずからを封じ込めるいとなみ」をやってみたい!と考えて生まれてきたのが、「津軽懇氣刺し」というプロジェクト。
毎年、立冬から立春まで、革ジャンにひたすら鋲を刺し続けるだけのことなんだけど、それだけっていうのが結構大事だったりする。意味はない。意味を取りにいかない。それだけが全て。このいとなみによって、僕は、時間そのものに自らを溶かし込むことを実感できるだろうか。このいとなみによって、僕は「何を待つでもない〈待つ〉」に近づけるだろうか。自分でやってみるしかない。
※「懇氣(こんき)」は、夏目漱石『行人(こうじん)』で使用されている言葉(たぶん漱石の造語)から拝借した。「ねんごろ」とか、「心をこめて」という意味になると思うけど、そこに祈りや希いが折り重なっていくようなイメージ。
何もない春です。
「襟裳岬」がヒットした当時、えりも町の方々から、「何もないとは何事だ」とずいぶんクレームの電話が入ったとwikiに記載されている。
黙りとおした 歳月を
ひろい集めて 暖めあおう
襟裳の春は 何もない春です
(歌:森進一・作詞:岡本おさみ・作曲:吉田拓郎・1974年)
曲の冒頭で、「悲しみを暖炉で」燃やす。さらに「黙りとおした 歳月を ひろい集めて」暖めあう。この燃やすことも、暖めあうことも「何を待つでもない〈待つ〉」ための、「機械のような時間のうちにみずからを封じ込めるいとなみ」のように思えてくる。
やがて、その悲しみが燃え尽きた頃には春がやってくる。何もない春。「何を待つでもない〈待つ〉」の先にあるのは、「何もない春」だ。「何もない」は、「無限にある」と同義だろう。それは雪国の僕らに必要な「くぐる時」だ。この「くぐる時」があるから、再生できる。立ち直る。何度でもやり直せる。
窓の外を見ると、いつの間にか、ぼんやりと光に包まれた無彩色の世界に、彩色が戻ってきている。ゆっくりと世界の輪郭が浮き上がってくる。土、木々、草、アスファルト、屋根でさえ、きっと「何を待つでもない〈待つ〉」を続けてきた。
去年のことはすっかり忘れてしまった。
ここからまた生きよう。
北国には悲しみを暖炉で燃やす時がある。
![]()
![]() 小山田和正 linktr.ee
小山田和正 linktr.ee
一般社団法人WORKSHOP VO 代表理事
元)東日本大震災津波遺児チャリティtovo 代表
法永寺(青森県五所川原市)住職
FMごしょがわら「こころを調える(毎週月13:05)」