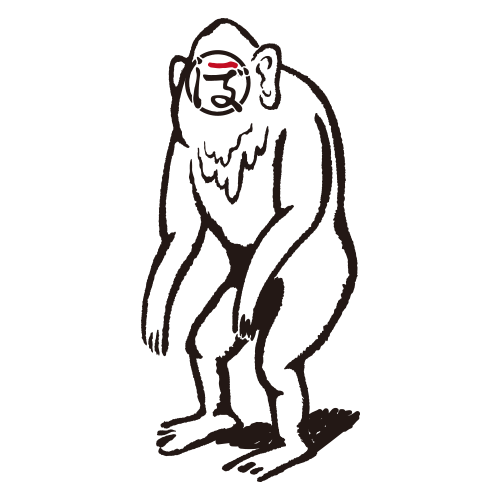㉗「脇道にそれること」
㉗「脇道にそれること」
HOME ‣ 連載 | サルサソース ‣ ㉗「脇道にそれること」 (2025.7.1)
さて、こうしてパソコンの前に座って「さて」と書き出してはみたものの何を書こうかとかはまったく考えもせずにこうして書き始めてみた。
今日は青森から東京へ来ていて、その経緯はあとにでも書いてみよう。早朝に到着した夜行バスを降りて、そのときはまだ7:00ころ外は涼しかった。朝ご飯でも食べようと思って東京駅の中をうろついてパン屋さんに入って3時間くらい経っていた。
「歩く-マジで人生が変わる習慣」を読み進めていて、最後のあとがきを読んで、そのあとはぼーっと過ごしていた。なんで、この本読み始めたんだっけな~と考えてみる。
WORKSHOP VO!! でもロングトレイルしようって話が上がっていたからだと思う。「歩くという哲学(フレデリック・グロ著)」という本も少し読み進めていたけど今は止まっている。歩くことの効用やなんかはさんざん語り尽くされていれるし、本にも書かれているから今更ぼくが書くこともないだろう。
青森の六ケ所村の泊(とまり)という場所で育ったぼくにとっては、歩くことだったり、自然の中に身を置くことは小さい頃から日常的なものだった。友達の家に遊びに行く、友達と磯に行く、港にいく、藪の中に開けた秘密の場所を探したり、こぢんまりとした泊という地域は子供が歩いて動き回るには広すぎず狭すぎず、ちょうどいい大きさの街だった。
6月、今からほんの一週間くらい前に友人の訃報が届いた。保育園、小中高とけっこう長い時間をともに過ごしてきた。社会人になってからはなかなか会う機会も減って、数年に一度地元の同級生たちと顔をあわせるくらいになっていた。そんな時に届いた知らせで、久々に地元に帰っていた。
ぼくら友人や家族などにしてみればとても悲しい亡くなりかたをしてしまった。最近読んでいたオープンダイアローグにかんすることが頭に思い浮かんだりもして、そうなる前に、その場がなければ意味がないし、その場に足を踏み入れてみようと本人が思わないことにはその効果も発揮できないのだなとも思った。周りの誰かが知っていてそこに誘い入れることができたらまた違ったのだろうかと、あとになって考えてもこの現実は変わることはない。
地元に戻って火葬が行われるまでしばらく時間があった。なんとなく、彼の実家まで歩いていってみようと思った。小学校の時、中学校の時、テレビゲームをしにいったり、漫画を読みに行ったり、よく遊びに行った。海沿いを歩いてみたり、山側から降りてみたり、近道だとしょうして他人の家の敷地のなかを通ったり、いろんな道を通って行ったことを思い出した。
その頃から脇道にそれることがとても面白かったんだろうな。大きな通りを進めば間違いなく到着するし、時間のことを考えたら脇道になんてそれる必要もないんだけど、いつも通らない道には面白いものが転がっている。まぁそんなことも大真面目に考えてなんかもいなかったと思う。たぶん。単純に、なんとなく、「今日はこっち行こう~!」なんて。ただそれだけだったんだと思う。
大人になると「なぜ?」「どうして?」「なんのために?」やら、その行動の根拠を求められる。いや求められすぎる。「なんとなく」はほとんどの場合許されない。そんな見えない要求がぼくらから脇道へそれることを奪ってしまう。いや逆に脇道にそれることをとても恐ろしいことのように感じてしまう。大きな道を歩いていなければならない、それてはいけない、まっすぐに歩くことはいつからメインストリームになってしまったのか?
ぼくらは皆、肉体的な死に向かって生きている。それを目的地とするなら、行き着く場所はだれもが一緒ということになる。友達の家が目的地であったように行く場所は決まっていても、そこに至るにはたくさんの道があった。道の途中で脇道にそれることも、進んでいた道が何らかの理由で通れなくなってしまったのだとしたら、来た道を戻って違う分かれ道を選んで進んでいく。
これですらも「友達の家」という目的がなければ、脇道もないということに繋がってしまうかw
いつでも「目的」や「目標」なんかに縛られてしまうのだとしたら、やっぱり、「脇道」のようなものが必要だ。いや脇道は無数に存在するんだけど、そこへそれることを拒む力がぼくらの内側から働いたり、外側から押し戻されたり、引っ張られたりする見えない力が働いているから、見えていても強い抵抗力が必要になる。もしくは、脇道すらも見えない、気づくことができなくなるほどに心を痛めてしまっている可能性もある。
脇道にそれることを楽しむ大人、それでも良いよねって思える人達、そんな人達が増えた来た時、また違った社会になっていくのかな?そのためにも、いろんなことを受け入れられるメンタリティを作っていく?そういうのすらも違っているような気もするけど。う~ん分からない。
人間として成熟していくことは必要だなとは思う。人間として成熟するってどういうことなんだ?
疑問は増えるばかりだ。友人の死に悩む必要はないと思うけれど、考え続けなきゃいけないことではあるんだと思う。ぼくらはどうあったらいいのだろうか?
ぼくら一人ひとりの在り方が、出会う人達に影響をあたえ、またそれが繰り返し、人間の社会、地球という社会を作っていく、のだとしたら、自分自身はどうあったらいいのか?というというころにまた戻って来る。
そんな風に、いろんな物事に影響されあいながら、変化していく。
単一なものが、まず自分と同じものを複製し、ついで多様化することによって自己組織化していく。それが充足した閉鎖構造を作ると同時に外界からの情報を取り込み、自己言及的に拡大していく。これが前章で述べた「超システム」の基本的な性質であった。
〜多田富雄 著「生命の意味論」
生物は同じものを複製していくかのように思えるし、最初の段階ではそうなのかもしれないけれど、場所によって、その周辺にあるものによって、同じDNAであってもその読み方を変え様々なものに変化していく。
偶然や後天的な経験を通して、生物はDNAの利用の仕方を変え、遺伝子を異なった文脈で読みかえるようになるのだ。
〜多田富雄 著「生命の意味論」
人間の素になっているものがそんな風なんだから、それを使ってこうして考えている、生きている「わたし」も、「これが私なんだ」と思えるようなDNA的なものであったとしても、やっぱりその見方を変え、生き方を変えていくことができる。頑なに変化をしないことの方がむしろ生きるということから遠ざかっていってしまうのかもしれない。
と最近読んでいたいろんな本に繋がっていく、いやただ無理矢理につなげたいだけなのかもしれない。そんな風にして友人の死はなんだったんだろう?とその意味を問いたいだけなんだと思う。
目次へ | 次へ

赤石嘉寿貴
生まれは大阪、育ちは青森。自衛隊に始まり、様々な仕事を経験し、介護の仕事を経て趣味のキューバンサルサ上達のためキューバへ渡る。帰国しサルサインストラクターとして活動を始める。コロナ禍や家族の死をきっかけに「生きる」を改めて考えさせらた。2023年3月愛知県新城市の福津農園の松沢さんのもとで研修を終え、現在は山について学ぶべく新城キッコリーズにて木こりとして研修中。 Casa Akaishi(BLOG)