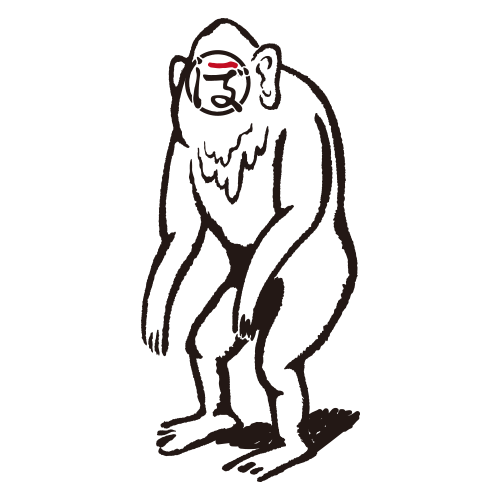【報告】2025年1月28日「SUBURI STUDIO」開催致しました。
HOME ‣ PROJECT ‣ SUBURI STUDIO

正会員・サポーター会員
2025年1月28日(火)21:00〜22:30、本年初回となる正会員・サポーター会員によるオンラインミーティング「SUBURI STUDIO(月1回開催)」を開催致しました。
今晩の参加者は3名。お知らせ(【告知】2024年1月「SUBURI STUDIO」のお知らせ)しておりましたように、今回は前回からの続き、鷲田清一著『「聴く」ことの力-臨床哲学試論』第5章〜6章を読んでいきました。
今日の主なトピックは以下になります。
今回語られたトピック(ファシリテーター:赤石嘉寿貴)
・他者のこのよう切迫にふれつつそれを忘れること、判断を停止することは、それだけでもう他者への暴力になりうるわけだ。
・流れをとめるってことが暴力?
・余命わずかの人の切迫にふれたときに問われる。どうせ死ぬのになぜ生きるのか?あなたはどう考えるか?
・問が自分の中で反響し続けている。
・「問い糺し」は他の人の苦しみにふれた時の感覚に近い。ぐるぐる思いだされるそれを止める糸口はどこにあるのか。
・注意をもって聴く耳があって、はじめて言葉が生まれるのである。
・自分のところに寄ってくるのはなんでなのか?
・亡くなってからも音は聞こえる。人は音を聞いて始まりと音を聞きながら終わる。
・「聴く」というのは音だけを捉えようとする行為なのか?
・手話には「机」「家」はあっても「家具」はない。
・この世界に接触していく仕方って色々ある。
・音は私が他者とともにそこへと住み込んでいる共通のエレメントのようなものだ。
長い時間をかけ、頭を抱えながらウンウンと読んできたこの本も、ついに最終章。次回は、7章〜8章を読んでいきます。
正会員・サポーター会員の方にご参加いただけます。お気軽にご参加ください。
「聴く」ことの力 ─臨床哲学試論
 「聴く」ことの力 ─臨床哲学試論
「聴く」ことの力 ─臨床哲学試論
著/鷲田 清一
発行/2015年4月8日
「聴く」―目の前にいる相手をそのまま受け止めるいとなみが、他者と自分理解の場を劈く。本書は、不条理に苦しむこころからことばがこぼれ落ちるのを待ち、黙って迎え入れる受け身の行為がもたらす哲学的可能性を模索する。さらにメルロ=ポンティ、ディディエ・アンジュー、レヴィナスなどを援用しつつ、ケアの現場や苦しみの現場において思考を重ねることで、「臨床哲学」という新しい地平を生み出した。刊行以来、多くの人に影響を与えた名著が文庫で登場。第3回桑原武夫学芸賞を受賞。植田正治の写真とともに贈る。
目次
第1章 “試み”としての哲学
第2章 だれの前で、という問題
第3章 遇うということ
第4章 迎え入れるということ
第5章 苦痛の苦痛
第6章 “ふれる”と“さわる”
第7章 享けるということ
第8章 ホモ・パティエンス
HOME ‣ PROJECT ‣ SUBURI STUDIO