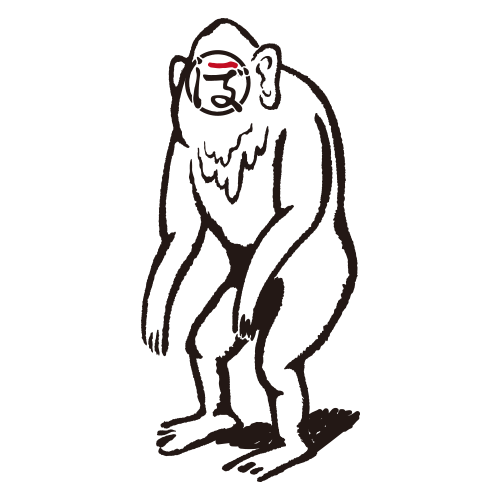【報告】2024年11月21日「SUBURI STUDIO」開催致しました。
HOME ‣ PROJECT ‣ SUBURI STUDIO

正会員・サポーター会員
本日、2024年11月21日(木)21:00〜22:30、正会員・サポーター会員によるオンラインミーティング「SUBURI STUDIO(月1回開催)」を開催致しました。
今晩の参加者は4名。お知らせ(【告知】2024年11月「SUBURI STUDIO」のお知らせ)しておりましたように、今回は前回からの続き、鷲田清一著『「聴く」ことの力-臨床哲学試論』第4章〜5章を読んでいきました。
今日の主なトピックは以下になります。
今回語られたトピック(ファシリテーター:赤石嘉寿貴)
* 言葉が質量をもっている感じ
* 「まとめ」の交換、「物語」として「まとめ」ること
* コーラスやオウム返し、けいひつの類似点
* 宇野千代さんの新聞のでの人生相談を読み、メールでの相談でも同じことができるのではないかと思った。
* わたしに語りかけてれている、という感触が大切なんだとおもう。聞いてもらえた、というその実感が大事なのだと思う。
* 聞かれたら返す、それはちゃんと受け止めましたよというメッセージになる。
* 「わたし」と<わたし>、1秒後のわたしはもう違うわたしになっている。
* 傷つくことに自分がいない。
* 変えられてしまうから傷つく。
今回は、第4章〜5章と設定しましたが、「第4章 迎え入れるということ」について、いったりきたりと繰り返し深めていくような時間となり、この章の話だけで時間いっぱいとなってしまいました。次回は、もう一度、第5章からになります。
正会員・サポーター会員の方にご参加いただけます。お気軽にご参加ください。
「聴く」ことの力 ─臨床哲学試論
 「聴く」ことの力 ─臨床哲学試論
「聴く」ことの力 ─臨床哲学試論
著/鷲田 清一
発行/2015年4月8日
「聴く」―目の前にいる相手をそのまま受け止めるいとなみが、他者と自分理解の場を劈く。本書は、不条理に苦しむこころからことばがこぼれ落ちるのを待ち、黙って迎え入れる受け身の行為がもたらす哲学的可能性を模索する。さらにメルロ=ポンティ、ディディエ・アンジュー、レヴィナスなどを援用しつつ、ケアの現場や苦しみの現場において思考を重ねることで、「臨床哲学」という新しい地平を生み出した。刊行以来、多くの人に影響を与えた名著が文庫で登場。第3回桑原武夫学芸賞を受賞。植田正治の写真とともに贈る。
目次
第1章 “試み”としての哲学
第2章 だれの前で、という問題
第3章 遇うということ
第4章 迎え入れるということ
第5章 苦痛の苦痛
第6章 “ふれる”と“さわる”
第7章 享けるということ
第8章 ホモ・パティエンス
HOME ‣ PROJECT ‣ SUBURI STUDIO