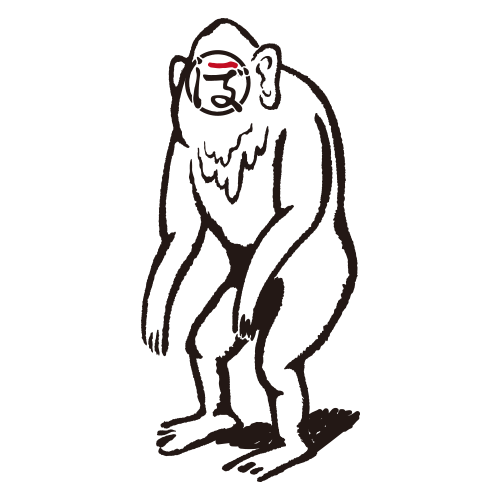【報告】2024年10月28日「SUBURI STUDIO」開催致しました。
HOME ‣ PROJECT ‣ SUBURI STUDIO

正会員・サポーター会員
本日、2024年10月28日(月)21:00〜22:30、正会員・サポーター会員によるオンラインミーティング「SUBURI STUDIO(月1回開催)」を開催致しました。
今晩の参加者は4名。お知らせ(【告知】2024年10月「SUBURI STUDIO」のお知らせ)しておりましたように、今回は前回からの続き、鷲田清一著『「聴く」ことの力-臨床哲学試論』第2章〜3章を読んでいきました。
今日の主なトピックは以下になります。
今回語られたトピック(ファシリテーター:赤石嘉寿貴)
•他者を経由することで内側から超えでてゆくこと
•自分に自信がなくてオウム返しができないんだと思った
•いかなる人間関係であれ、そこには他者による自己の、自己による他者の「定義づけ」が含まれている
•歩いて話をすると景色が流れていく、景色という余白に逃げ込める
•オウム返しネクスト
•一緒に歩くにはお互いの歩幅を調整したり、スピードに合わせたり、この時相手はすでに自分の中にいるし、相手の中に自分もいる。
•他人の世界のなかでの場所を必要としているように思われる
•「だれかがわたしに一杯のお茶をくださったなんて、これが生まれてはじめてです。」なんていわれることはあったか?
今回は、第2章〜3章を読んでいきましたが、短い文章の中にも、理解の及ばない箇所や、聞きたい話したい箇所が多く、ああでもないこうでもないと、ひたすら悩みながら、ゆっくり進んでいきました。次回は第4章からになります。
正会員・サポーター会員の方にご参加いただけます。お気軽にご参加ください。
「聴く」ことの力 ─臨床哲学試論
 「聴く」ことの力 ─臨床哲学試論
「聴く」ことの力 ─臨床哲学試論
著/鷲田 清一
発行/2015年4月8日
「聴く」―目の前にいる相手をそのまま受け止めるいとなみが、他者と自分理解の場を劈く。本書は、不条理に苦しむこころからことばがこぼれ落ちるのを待ち、黙って迎え入れる受け身の行為がもたらす哲学的可能性を模索する。さらにメルロ=ポンティ、ディディエ・アンジュー、レヴィナスなどを援用しつつ、ケアの現場や苦しみの現場において思考を重ねることで、「臨床哲学」という新しい地平を生み出した。刊行以来、多くの人に影響を与えた名著が文庫で登場。第3回桑原武夫学芸賞を受賞。植田正治の写真とともに贈る。
目次
第1章 “試み”としての哲学
第2章 だれの前で、という問題
第3章 遇うということ
第4章 迎え入れるということ
第5章 苦痛の苦痛
第6章 “ふれる”と“さわる”
第7章 享けるということ
第8章 ホモ・パティエンス
HOME ‣ PROJECT ‣ SUBURI STUDIO